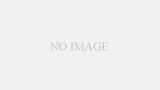昨今さまざまな企業でも問題視されてる「きつい運送業界」。
実際のところ多くが「これだ」という定義付けはあってないようなものであり、国側としてもその辺りを明確にはしてないというのが現実です。
今回は少しシリアスなテーマとなりますが、運送会社でも問題視されてるきつい企業の現実をホワイト企業を含めランキング別に見ていきます。
ホワイト企業を探すならこちらから!

評判のいい運送会社ランキング一覧
評判のいい運送会社を評価順にピックアップしました。
評価は某大手転職サイトの口コミ評価より抜粋しています。
口コミ評価のため順位は常に変動します。
定期更新を心掛けていますがご了承ください。
1位.シモハナ物流株式会社
2位.樋口物流サービス
3位.日立物流
5位.有限会社アムトラックス
6位.ハコブ株式会社
7位.成田運送株式会社
8位.センコー運輸株式会社
9位.ヤマト運輸株式会社
10位.国際コンテナ輸送株式会社
11位.京王運輸株式会社
12位.丸進運輸株式会社
13位.協和コーポレーション株式会社
14位.株式会社南日本引越センター
15位.やよい運送株式会社
16位.安田運輸株式会社
17位.名鉄運輸株式会社
18位.フェデラルエクスプレスジャパン
19位.西濃運輸株式会社
20位.DHLジャパン
運送会社のホワイト企業ランキングはどこ?
「長きにわたる労働時間の恒常化」や「社内での社員に対するハラスメント」、「残業代や各手当の未払い」など結果として入れ替わりの激しい会社になり、実状としてもこのような問題は運送会社においても多数報告されております。
ただそれは運送会社を含めすべての企業がきついという訳ではなく、国が定めた労働基準法に正しく則り「ホワイト」として運営してる企業も多数存在します。
次にその多数あるホワイト企業の中で最も多く名が挙げられた運送会社として、倉庫業なども含めランキング別に3社を見てみます。
1位 上組(兵庫県)
2位 キムラユニティー(愛知県)
3位 三菱倉庫 (東京都)
この3社に共通している事としては平均勤続年数が14~18年とされ、20年には満たないものの殆どの従業員では比較的安定した勤務年数としても定評があります。
年収についても3社とも共通するのが「やや多めの額」であり、さらにその年収は3社とも「上昇傾向」となってます。
運送会社のいじめの現状とは
ドライバーの場合であれば日中のほとんどが基本一人ぼっちの運転業務であり、あまり人間関係のもつれなどは事務職と比べれば少ない印象となってます。
ただそれ故に気楽な性分があだとなり、コミュニケーション不足なところが誤解を招く結果ともいわれてます。
「運送会社内でのいじめ」といっても他の会社同様にさまざまなケースで起こり得ますが、よく聞かれるものとしては「本人直接ではなく間接的」に「自ら退職するよう仕向ける嫌がらせ行為」が最も多いとして報告を受けてるようです。
男女問わず一見するだけでは判って貰えない様な嫌がらせも「本人にとって耐え難い思い」をさせられたのであれば、それは紛れもなく「いじめ」となります。
ただ運送業界においても「陰湿極まりの無いいじめ行為」など、悲しい事ですが現実問題としては今後も無くなるとは思えません。
やばい会社に入社した時の対処法
この場合での結論から言うと「即退職」正直これが一番の対処方法となります。
ただ一番の対処方法といってもそれがすべての人に該当しないのは言うまでも無く、各々の生活事情というのも大きく関わってくるため実際には簡単に辞めれないものです。
ですが冷静に考えてみて下さい、例えばそのやばい会社というのが運送会社であり、そこに「体が資本のドライバー」として勤務されてるのであれば尚更その資本となる体を自身で守らなければなりません。
法律や企業におかれたそれぞれのガイドラインによってある程度は「守られてる気でいれる制度」というのはあれど、まずは「自分の身は自分で守る」という事から入りましょう。
それが例え肉体労働でなくとも結局は体が資本となり、結果としては「体や精神面が健康であればすべてはやり直しが利く」という事になり得ます。
まとめ
今回のテーマでもある運送会社のきつい・ホワイト企業についての判断基準はあくまで個人の価値観からくる情報にしか過ぎず、信憑性としては怪しい情報も多数あるのも事実。
でもって実際には「そんなにひどい会社という訳ではなかった」というのも少なからず報告されております。
ひどい会社やいじめ問題などの定義付けは非常に難しく、どこで線引きしていいのか分からないものですが「蔓延る情報」のみに惑わされるのではなく、自身の体験こそが「揺るぎない真実」であると言えるでしょう。